安全保障関連法(安保法制)の成立から10年。北海道から沖縄まで110人の女性たちが、その違憲性を訴え、国家賠償を求める裁判が続いています。通称「女の会」訴訟。11月12日に第8回口頭弁論が東京高裁(谷口豊裁判長)で開かれ、証人尋問と意見陳述に基づく控訴人尋問がありました。安保法制は暮らしにどんな影響を与えているか、2人の意見陳述と尋問から振り返ります。
安保法制違憲訴訟 2014年、安倍晋三内閣(当時)は従来の政府の憲法解釈を覆し、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を行い、2015年9月に安保法制が成立した。その後、安保法制は、①憲法が定める平和的生存権を侵す ②憲法13条の幸福追求権を侵害し、個人の人格権を損なう ③憲法96条が定める改憲手続きを経ておらず、国民の改憲に関する意思表示の機会を奪った——などの理由で、市民らが全国各地で国家賠償請求訴訟を起こした。地裁や支部に計25件の提訴があり、1700人が原告となった。最高裁で上告の棄却や不受理となったものが18件、高裁で原告敗訴が確定したものが5件。現在、東京高裁で「女の会」訴訟、名古屋高裁で愛知訴訟が継続中。
「女の会」訴訟は、2016年8月15日に東京地裁に提訴。原告121人、代理人9人は全員女性。東京地裁の武藤貴明裁判長は2022年1月28日、判決前に原告側3人の意見陳述のあと、弁論を聞かずに退廷しました。その後、一方的に判決期日を同年3月25日に指定したため、原告側はボイコット。原告不在のまま、原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。原告側は控訴し、東京高裁で審理が続いています。
11月12日の控訴審はおよそ1年ぶりの開廷。この日は学習院大学専門職大学院法務研究学科の青井未帆教授による、安保法制の違憲性にかかる証人尋問と、控訴人2人の意見陳述と本人尋問がありました。その要旨を採録します。
1人目は千葉県船橋市の市議会議員、金光理恵さん。質問は山本志都弁護士です。
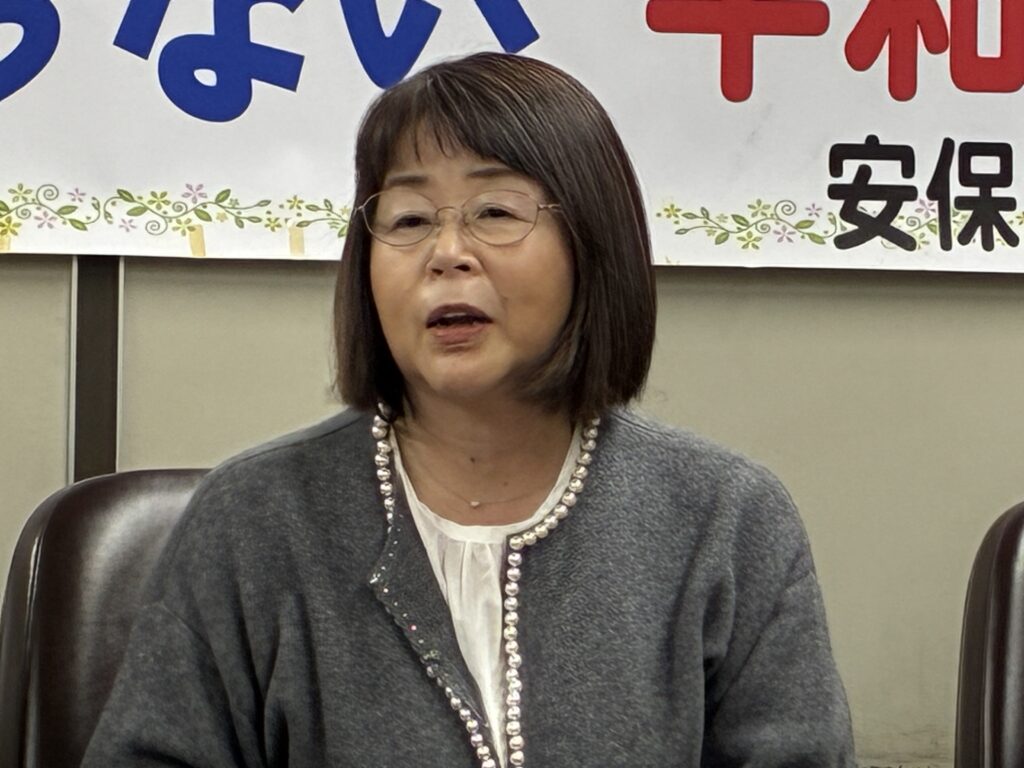
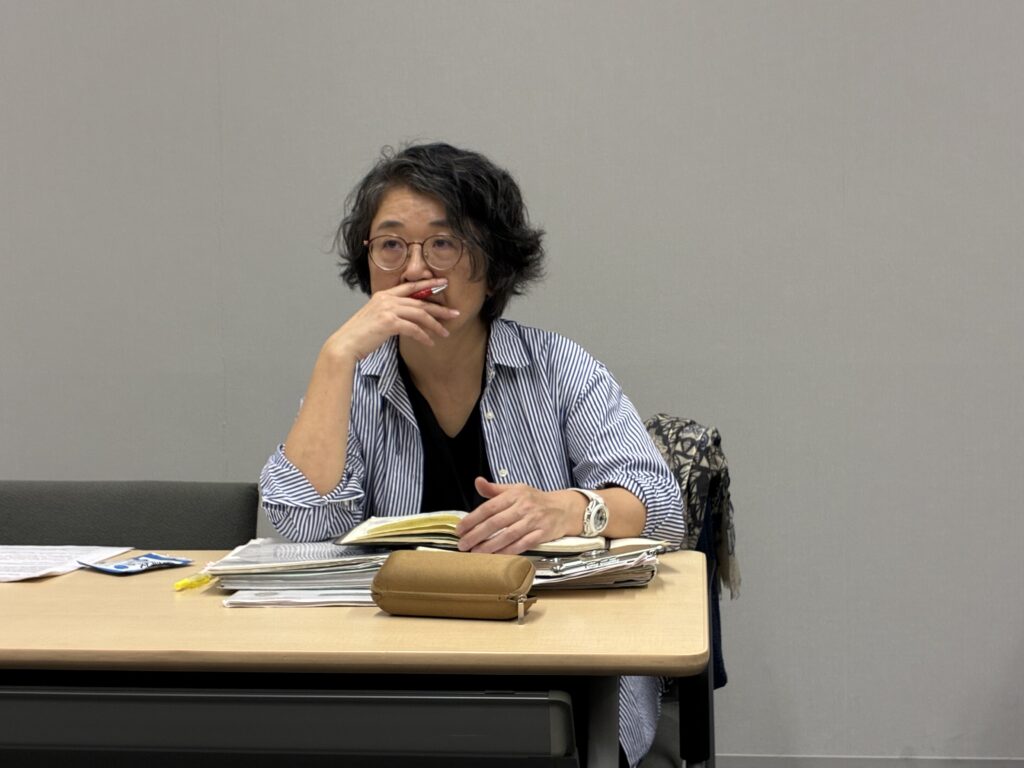
自衛隊駐屯地のある町で平和的に暮らしたい
Q)あなたと安保法制のかかわりについて
A)2023年4月から船橋市議を務めている。市議として、自衛隊習志野駐屯地のある町で平和的に暮らしたいという市民の権利を守るため、努力してきた。
Q)安保法制の施行後、習志野駐屯地にはどんな変化があったか?
A)訓練の回数が増え、内容も実戦的になった。習志野駐屯地には、火薬庫・弾薬庫があり、地上から弾道ミサイルを撃墜するパトリオットミサイル(PAC3)が配備されている。2023年度から総額4兆円を投資して、10年以内に全国の自衛隊基地などを、化学兵器、生物兵器、核兵器などの攻撃に耐えられるようにする「基地強靱化」が始まった。核攻撃に備え、地下シェルターを設置するというが、避難できるのは司令部のみ。周辺住民の安全は守られない。基地(駐屯地)があることで攻撃を呼び込み、住民が巻き込まれる事態が想定される。
騒音やパラシュート落下ミスが生活に影響
Q)習志野駐屯地にはどのような部隊が配備されているか?
陸上自衛隊の第一空挺団が駐屯している。精鋭無比といわれ、自衛隊で唯一の1900人が配属されるパラシュート部隊だ。そのほか特殊作戦群という秘密部隊があり、300〜400人がゲリラ戦・密着戦の訓練をしているというが、詳細は明らかにされていない。双方とも組織上は大臣直轄の「陸上総隊」に位置づけられている。それだけ重要な位置づけで、都心から1時間ほどで来られる。
Q)駐屯地の近隣の住民にはどのような影響があるか?
A)弾薬庫・火薬庫、PAC3があることで、有事があれば真っ先に狙われる可能性がある。
平時でも生活の中で騒音やパラシュート落下ミスの被害を受けている。
航空機は朝7時25分に飛び始め、8時半から正午まで、午後も2〜3時間、酷いときは夜間も2時間訓練が続く。この地域には学校が50校ほどあるが、上空を航空機が飛ぶため、数分置きに教員の声が聞こえない。船橋市の騒音測定の結果は文部科学省が定める学校安全衛生基準よりも高いレベルになっている。射撃音、大砲の音が登校時に聞こえる。子どもが怖がっている。
パラシュートの場外降着は頻繁に起こっている。民家の屋根、高校のグラウンド、交通量の激しい県道、会社の事務所に落ちたこともある。一歩間違えば大惨事だ。

Q)演習場の面積と降下訓練の状況からどのようなことが言えるか?
A)第一空挺団の訓練場所は住宅街のど真ん中にあり、非常に狭い。しかし、降下回数はケタ違いに多い。上空を飛ぶ航空機のスピードは新幹線の速さ。そこから飛び降りるので、1秒、2秒の遅れが場外降着につながる。
なぜ習志野が訓練場所とされたのか? 住宅地のど真ん中にあり、市街地の戦闘訓練に最もふさわしいからではないか。
外国軍との共同演習が激増
Q)安保法制の成立後、どのような変化があったか?
A)外国軍との共同訓練が積極的に実施されるようになった。米国をハブとして多国籍の軍隊との軍事訓練が行われることによって自衛隊駐屯地の米軍基地化が進んでいる。
習志野駐屯地では年頭に「降下訓練初め」を行うが、2017年から沖縄駐留米軍が加わり、2023年からイギリス、オーストラリア軍が参加。2024年は7カ国、2025年は11カ国が参加した。2025年から主催も第一空挺団から陸上幕僚監部に変更された。
2020年9月からは米軍との共同演習が横田基地で始まった。横田基地まで習志野駐屯地の第一空挺団隊員が移動して、米軍輸送機(C130J)に搭乗し、20分後に習志野訓練場の上空からパラシュート降下する。米側が公開した動画によると、「ジャンプ!」と米軍兵士が、自衛隊員に指示を出している。米軍の指揮で自衛隊員が闘わされるということを目の当たりにした思いだ。
2025年9月には習志野演習場でオリエントシールド2025が開催された。日豪の共同情報収集訓練だ。オーストラリア軍はパラシュート降下訓練やドローンを使った訓練を自衛隊と共同実施した。前後を含む15日間、オーストラリア軍兵士が駐屯地に滞在することがわかり、私たちは、兵士たちが基地の外に単独で出歩いたり飲酒などをしないように防衛大臣に申し入れた。
Q)特殊作戦団について、どのような心配があるか?
A)陸上自衛隊の対ゲリラ戦部隊「特殊作戦群」と海外派遣の先遣隊「中央即応連隊」を統合し、来年度に「特殊作戦団」が新たに編成され、その本拠地が習志野に置かれる。陸将補をトップとする1200人体制の組織だ。人の生命を奪う訓練を繰り返すようなストレスの大きな職務につく自衛隊員が増える。自分たちは自衛隊員の人権や命を守りたいという思いで活動してきたので、さらに大きな負荷がかかることを心配している。
迷彩服で通勤 市民は慣れっこに
Q)自衛隊が市民生活に浸透してきている様子について
A)駐屯地の外に住んでいる自衛隊員は戦闘服・迷彩服で通勤するようにとの通達が出ている。市民は慣れっこになってしまった。小学校にも迷彩服の人が出入りしており、あるとき学校に子どもを迎えに来た全身迷彩服の人をふと見たら、女性だった。私は「誰の子どもも殺させない」と活動をしてきたが、このとき「誰のお母さんも殺させない」と考えを新たにした。
また、迷彩服を着た自衛隊員が小学校で防災講話を行ったり、学校プールの掃除をボランティアで行ったりしている。市民祭りでは子どもサイズの迷彩服が用意され、それを着た子どもたちが自衛隊車両に乗って記念撮影をし、アンケートに協力した少年には入隊までマンツーマンでリクルーターが付くなど、将来の自衛官確保の場となっている。
自衛隊が中学校の職業体験を受け入れ
Q)中学校の職業体験でも自衛隊に行くことがある?
A)第一空挺団の協力下に「空挺少年団」が組織され、中学校の職業体験を受け入れている。昨年は3校から33人が参加した。歴史知識や判断力の未熟な中学生の体験する職場としてふさわしくなく、国際法上のルールにも反すると市議会で指摘したが、市は「一般の企業での職業体験と同じ」と答弁した。
Q)自衛隊のリクルート活動について
A)高校卒業時の18歳を対象に、自衛隊からダイレクトメールが送られてくる。住民基本台帳から年齢で絞って抜き出している。船橋市は閲覧をさせているが、名簿提供までは行っていない。団地(市営住宅)がある地域が閲覧の対象になっている。経済的に厳しい家庭の子どもを狙いうちにした経済的徴兵制の問題がある。高卒で正規雇用されるのは自衛隊ぐらいで、高卒生の7割が自衛隊を就職先の候補に考えている。
地方は国のいいなり 市議の仕事が歪められている
Q)安保法制は地方自治にどのような影響があったか?
安全保障に関しては、地方自治の力が薄れ、国のいいなりになり、何も言えなくなっている。全くといっていいほど、情報が下りてこない。市議会で質問をしても「国の専管事項」とはねられてしまう。国会議員を通じて防衛省から聞き取りをすれば回答を得られるが、「部隊の運用に関わること」「米国側のことなので防衛省は知らない」など核心部分については答えない。
住民の安全・安心のための情報が把握できない。住民福祉に注力できないほど、市議の仕事が歪められていると思っている。
2024年に地方自治法が改正され、解釈によって自治の権能が大幅に制約されてしまう。
「戦争する国」になるために、国は自治体を縛り、市民の人権侵害を重ねている。「住民自治」の破壊が起きている。基地により、住民の人権リスクが発生している中、それを低減させるのは市議の役割だ。その職責が果たせなくなっている状態が違法でないということはあり得ない。


