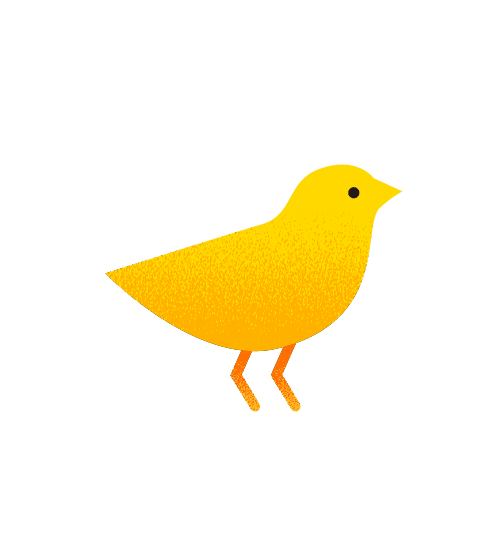仕事終わりに地元の市議とちょっと一杯—。地方議会と住民の関わりを促す少しユニークな取り組みが神奈川県茅ヶ崎市で進んでいる。市民と茅ヶ崎市議らがお酒を飲み交わしながら対話する催し「まちのBAR」が4月4日、市内のコミュニティスペースで開かれ、2023年7月の開催から20回を数えた。市民有志でつくる実行委員会などが主催し、延べ約700人が参加。カフェや駄菓子屋など市民から開催場所を募りながら市内各所へ取り組みを広げている。今後は街や市政の課題について少人数で対話をさらに深める企画を検討しており、市政や市議会への提案や働き掛けなど市民側の新たな動きにつなげる狙いだ。
4日、夕暮れ時のビーチを望む店内では、市内外から訪れた参加者約40人がテーブルを囲んだ。相づちを打つのは与野党、無所属会派から参加した市議や県議7人。紺色のエプロンに袖を通した「マスター」役の市議が参加者にお酒を運んだ。この日は「議員を続けていて良かったと思うことは?」といった個人的な質問から、「(商店などが立ち並ぶ)雄三通りの歩行者マナーを改善したい」「市内の農産物を給食や店舗で提供できないか」など市民の悩みや提案も飛び交っていた。
参加した市議の男性(61)は「移住者も多いので、普段は接点のない市民と話せるのが魅力。自分が知らなかった市民の実情を知ることもある」と話す。市内に移住して間もない鈴木みえさん(55)は「母親や子育てといった課題に関心があり、地域とつながるきっかけになればと思って参加した」。隣市の藤沢市から催しに通っているという菅原有梨さん(37)は「会社の上司と話すように市議さんの話を直接聞くことができて、とても新鮮。政治や予算の話も堅苦しさはなく、身近に感じられる」と楽しそうに語った。
まちのBARを呼び掛けたのは、茅ヶ崎市で街づくりに取り組む池田一彦さん(47)、美砂子さん(47)夫妻。10年ほど前に東京から移住し、2児の子育てをしながら、コミュニティスペースの運営などに携わっている。きっかけは、子どもたちの主体性を育む場をつくろうと前回市長選(22年10月)に合わせて企画した模擬投票の催し「ちがさきこども選挙」だった。美砂子さんは「政治的な目的の催しではないのに、『選挙』と言葉にするだけで、店舗などにチラシを置くことを断られてしまうこともあった。政治や選挙という言葉をはばかるような空気を感じた」と振り返る。一方、こども選挙には市内外の約60人がボランティアとして参加。子どもが街や市政について学んだり知ったりする機会を盛り上げたボランティアが、実際に市議選に立候補する動きが出た。一彦さんは「主権者教育を受けたのは子どもではなく、実は大人の方。変化の兆しを感じた」という。

23年4月の市議選を受けて、池田さんらは当落問わず立候補者を市民が囲むイベント「アフター選挙BAR」を開催。住民と地方政治との距離を近づけようとする機運が盛り上がり、「まちのBAR」の定期開催につながった。催しでは毎回、参加者に話したいテーマをカードに書き込んでもらう。発言できなかった意見や話題は、カードの画像をホームページやSNSで紹介し、参加者全体で共有している。これまでの催しでは、防災や環境問題、教育などさまざまな分野で活動する市民をゲストとして囲み、現場の声を聞きながら対話を広げてきた。市の津波対策について語った参加者の意見を基に、市議が一般質問で避難用のハザードマップを課題として取り上げるなど、地方議会の現場に声を届ける動きも生まれた。
対立や分断から抜け出すための3つの約束
池田さんによると、企画にあたって苦心したのが「誰もが安心して政治の話ができる場」づくりだ。まちのBARでは現在、「対立ではなく対話を」「批判ではなくアイデアを」「分断ではなく協力を」との3つの約束をうたい、参加者の対話を促している。
対立ではなく、対話を
「まちのBAR 会話ポリシー」より
批判ではなく、アイデアを
分断ではなく、協力を
昨年の東京都知事選や兵庫県知事選を巡っては、SNSによる真偽不明な情報や一方的な主張の拡散が問題視された。「互いの声を直接聞くこともなく、自分の意見が正しいと思い込んで発信することで言論の空間に分断が起きている」様子に危機感を覚えたという池田さん。「まちのBARで目にしてきた『対話』の価値や重要性をあらためて感じ、言語化したいと思った」と言う。政治の現場では、住民から見た行政や議員は「権力」として映り、政治側から見た住民は「クレーマー」として映ることも珍しくない。対立から抜け出すために必要だと考えた姿勢を、3つの約束にまとめた。
「まちのBAR」の取り組みは昨年、国内最大規模の政策コンテスト「第19回マニュフェスト大賞」のシティズンシップ部門で、優秀賞・審査員特別賞を受賞した。実行委は今後、新たな試みとして「まちのDIALOG(ダイアローグ)」と題して、少人数で子育てや防災、街の再開発など、具体的な政策テーマで議論を深める場を構想しているという。 まちのBARで交わされた意見を、「井戸端会議」にとどめることなく、地方議会や行政への具体的な提案や働き掛けにつなげる狙いもある。池田さんは「住民の共助だけでなく、地方政治の場に住民の声が届くことで変えていける課題もあるはず。まちのBARで生まれたつながりや対話を深めることで、社会を足元から変える仕組みをつくっていきたい」と話している。
コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています
生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、コモンズの活動をご支援ください。 → 寄付でサポートする