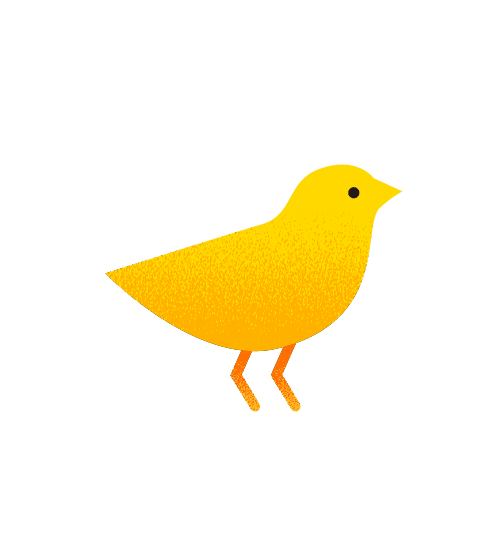毎朝、BSの世界のニュースでパレスチナ・ガザ地区の惨状が映し出される。目を背けたくなるような細い手足の子どもたち。食料が尽き、餓死を待つだけの人々。
そして、最初はギョッとしたあのナレーションにも慣れそうになっている自分が怖い。
「身体に危険が及ぶため、撮影者の名前は明かせません」
名前を消され、それでも撮影を続けるジャーナリストたち。その動機はどこにあるのだろうか。
そんなことを考えていた時、映画「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」を見た。
女が戦場に同行できなかった時代に
第二次世界大戦のヨーロッパ戦線を撮影した実在の報道写真家の伝記映画だ。主演のケイト・ウィンスレットは、遺族の協力の下、彼女の写真アーカイブを全て見て、物語を組み立てていった。
リー・ミラーは1907年アメリカ生まれ。VOGUE誌のモデルを務めた後、撮られるより撮る側になりたいと前衛写真家マン・レイに学び、独自のスタジオを開く。映画はこうした前半生を割愛し、1938年以降、リーがいかにして戦場ジャーナリストとなっていったかを描いている。
結婚し移り住んだイギリスでは、軍隊に女性が同行する許可が下りず、母国のアメリカに申請して取材パスポートを得た。それでも、最初は前線には出られず、キャンプ内で手足がちぎれた傷病兵や女性の補給隊員の姿を撮影した。

次に派遣されたサン・マロは内戦のまっただ中。命の危機にさらされながら、ナパーム弾が使用された爆撃の様子をカメラに収めた。ここで、女性たちが1人の女性をつるし上げている場面に遭遇する。フランス語で聞き取ると、ドイツ兵と寝た女性が「スパイ」「裏切り者」として糾弾されていた。サン・マロが陥落した翌日、町の人たちは彼女を取り囲み、バリカンで髪を刈った。リーはその情景も撮影した。
その後、連合軍の東進に従って、ドイツへ。ユダヤ人の強制収容所で、折り重なる何千人もの遺体を撮影し、ヒトラーが自決した後の邸宅の浴室で入浴写真を撮った。リーを象徴する一枚といえば、この入浴写真になるのだと思う。
連合国軍による解放に湧くパリで
だが、私が映画で最も印象に残ったのは、連合国軍により解放された直後のパリの場面だった。お祭り騒ぎに湧く街を歩いていたリーは、建物の陰から女性の悲鳴を聞き取る。駆けつけると、連合国軍の軍服を着た若い男性兵士が女性をレイプしようとしていた。リーがとっさに割って入り、持っていたナイフを突きつけると、兵士は「俺たちがパリを解放してやったんだ。感謝し、礼をしてくれたっていいだろう」と捨て台詞を吐いて去って行った。リーは女性にナイフを渡し、「次は切り落としなさい」と告げる。
重い気分を抱えて、ロンドンのVOGUE誌に電話をかけると、親友の女性編集長ですら、「そっちはどう?歓喜に湧いているそうね」と明るい声で応じた。

男性には見えない風景がある。その場にいなければ想像できない現実がある。戦時であればなおさら。
日本では今月、自民党の西田昌司参議院議員が沖縄のひめゆり学徒隊について、独自の歴史認識を示した。
「日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆり隊が死ぬことになっちゃったと。そして、アメリカが入ってきて、沖縄が解放された。そういう文脈で書いている。亡くなった人は報われない」
真の解放軍は誰か。男にとって重要なその部分は、女にとっては「どちらも同じ」だ。解放してやったんだと恩を着せ、レイプし、抑圧する。その構図に変わりはない。戦後、沖縄を占領したアメリカ軍も同じことをし、今も被害は続いている。
だからこそ、女性たちが撮り、書き、記録し続ける意味があるのだと思う。
「女のことを書かせない」に抗う
日中戦争(1937−45)時、陸軍の報道班に所属した作家の火野葦平は、戦後になって戦争報道における「書いてはならない7カ条」を発表した。
一、日本軍が負けているところを書いてはならない
二、戦争の暗黒面を書いてはならない
三、味方はすべて立派で、敵はすべて鬼畜でなければならない
四、作戦の全貌を書くことを許さない
五、部隊の編成と部隊名を書かせない
六、軍人の人間としての表現を許さない
七、女のことを書かせない
七は主に帝国軍人は性欲に負けることがないはずだという意味合いでの禁忌だったようだ。しかし、この戦陣訓の裏を返せば、「そこには女・子どもが生きている」「そして酷い目にあっている」と書き続けることが、戦争に抗う力となるということだ。

映画の冒頭で70代となったリーは若い男性記者からインタビューを受ける。「あなたは名声のために撮ったのか?」
「名声?そんなもののために写真を撮ったりしない」
そう、私たちがこのひどい世界を記録し続ける理由は、名前を売るためでも、飯の種を稼ぐためでもない。
「残酷だ」という理由で写真を封印しようとした社会に憤り、撮りながら自分の過去の性被害を見つめ直したリーの姿に、80年の時を超えてシンクロする現在の女性ジャーナリストたちを思う。ともに手を携えて記録を続けよう。女(わたし)たちはここにいる。
◇映画「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」(エレン・クラス監督)は、5月9日より東京・TOHOシネマズシャンテなど全国で公開中。
https://culture-pub.jp/leemiller_movie/index.html
コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています
生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする