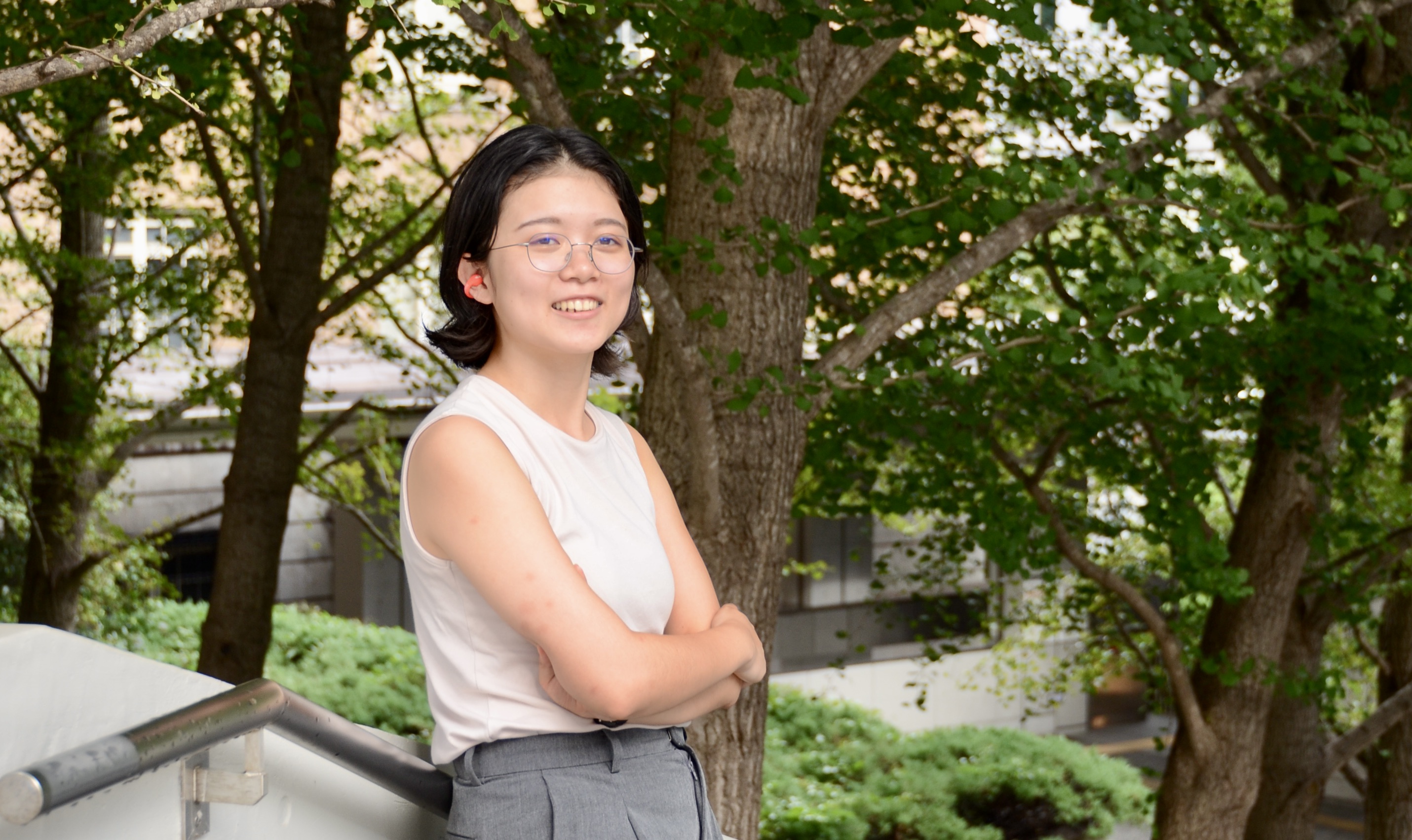10代が政策決定の場に参加するには
2018年、気候変動対策を訴えてスウェーデンの議会前で抗議を行う少女の姿が、SNSで話題を読んだ。グレタ・トゥーンベリさん=当時15歳=による運動は「未来のための金曜日(Fridays For Future:通称FFF)」と呼ばれ、日本を含む世界各地の若者による抗議運動が広まった。環境活動家の中村涼夏さん(23)も高校3年から運動を牽引した一人だ。「大きな経済や政治の歯車に対して、市民がきちんと意見を届け、政策決定できる。そうした仕組みの呼び起こしが気候変動対策には最も重要だと思う」。その思いを胸に今春、大学を卒業し、NGO職員として新たな道を歩み始めた。
鹿児島県指宿市に生まれ、父親の転勤に伴って5歳ごろから名古屋市で育った。幼少期から親しんだ鹿児島の海への思い入れは強く、海と生き物が大好きな子どもだった。研究者や国際機関の仕事に憧れ、市立高校へ進学。受験勉強の合間を縫って環境保護団体の催しに参加するなど、学外へも活発に顔を出した。初めて気候変動対策を訴えるデモに足を運んだのは、そうした高校3年の時だった。
スマートフォンを手に気候変動対策の実状を調べ始めると、「将来の問題ではなく、今を生きる自分たちに選ぶ責任がある」との思いが強まった。日本を含む各国は15年、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)のパリ協定で、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて1.5度に抑える「1.5度目標」に合意。しかし、先進国が示す二酸化炭素排出目標は、国際目標に整合する数値に遠く及ばない。世界の平均気温は、すでに短期的に1.5度に迫る気温上昇が観測され、災害や食糧危機、それらに伴う人道危機が現実となっている。

若者らが街頭で対策を訴える「気候マーチ」は当時、名古屋のほか、東京や京都を中心に全国で5千人の規模に上っていた。高校3年だった19年10月、中村さんは東京で開かれた気候変動対策を進めるリーダー育成を目指す研修会に参加。そこで初めて、各地で運動を展開する仲間たちに出会った。運動の中心を担う「オーガナイザー」と呼ばれる若者が連携を図る「Fridays For Future Japan(フライデーズ フォー フューチャー ジャパン)」を年明けに発足。「知識や経験が浅いという理由で、政策決定の場から遠ざけられている若者にとって、政治に声を届けるには自分たちのコミュニティ(共同体)が必要だった」と振り返る。
一方、塾や学校を休む日もあった中村さんに対して、両親の言葉は厳しかった。受験勉強や進路を巡って口論も増えた。「国立大に進学できなければ、就職しなさい」「女の子だから、県外で一人暮らしはさせたくない」。3姉妹で育ち、娘を心配する両親の気持ちは理解できた。それでも「自分が女でなければ、自分の選んだ道を応援してもらえたのかな」との思いは消えない。「女性である不自由さを初めて意識した」時期でもあった。
日本経済が与えるのは「発展」ではなく「損害」
鹿児島大水産学部に進学した中村さんは20年2月、 温室効果ガスの排出削減目標を掲げる「地球温暖化対策計画」について話し合う環境省と経済産業省合同の審議会に仲間と出席した。1.5度目標の達成に必要な62%の目標設定が必要だと強く訴えたが、反応は鈍かった。政府は21年、温室効果ガスの排出量を2030年度までに46%削減(13年度比)する目標を盛り込んだ計画を策定。中村さんは「政府や企業にとっての気候変動対策は、いつも経済政策の枠の中にある。世界的な格差や貧困に繋がる人道問題として捉える市民側との意識の隔たりは大きい」と話す。
中村さんは、エジプトで22年11月に開いた国連気候変動枠組条約締約国会議(COP27)を映像で伝えるプロジェクト「record1.5」を仲間と共に企画した。会場周辺で抗議の声を上げる各国の活動家たちの声を発信することで、日本の立ち位置を浮き彫りにする狙いだった。
「熱波やかんばつの被害を最前線で受ける私たちに賠償して」と街頭で声を上げるインド人女性。石炭火力発電所建設への資金協力を続ける日本のメガバンクや政府関係者を会場で問いただすアフリカやアジアの青年たち。主要先進国が石炭火力発電の段階的な廃止へ踏み切る中、途上国の石炭火力発電事業に資金や技術を注ぎ込む日本へ送られる視線が、映像を通して突き刺さってくる。
「日本が途上国に経済発展を迫ることで、人々の生活の糧や文化が失われていく地域がある。日本の加害性を意識せざるを得ない経験だった」と中村さん。連帯しようとしていた若者たちに日本人である自分が追求されているような感覚に、現地の会場では無力感から涙がこぼれた。

地域が利用するエネルギー 市民が選ぶ社会に
環境省と経済産業省は6月、次期の「温暖化対策計画」の審議を開始。エネルギーの電源構成を示すエネルギー基本計画の策定と並行して検討が進む。現在、中村さんらのグループが要望しているのは、1.5度目標の達成に向けて、2035年までの温室効果ガス削減目標を13年度比で78%とする大幅な引き上げだ。現在は電源構成の約2割を占める再生可能エネルギーの普及が鍵を握る。経済活動中心の議論に転換を迫るには「住民が利用するエネルギー資源を、住民自治の一環として自ら選ぶことができる仕組みをつくること必要だ」と考えている。
先例として注目する自治体がある。22年に環境NGO出身の岸本聡子さんが区長に当選した東京都杉並区だ。今春、就職に合わせて杉並区に引っ越した。岸本区長は気候変動対策を住民で話し合う「気候市民会議」の設置を公約に掲げており、実際に住民との対話の場へ積極的に足を運ぶ姿に刺激を受けた。一方、課題は「住民や議会の参加をいかに盛り上げるか」だと感じている。「いつか鹿児島で小さな自治体の首長になって、住民と一緒にこっそり良い街をつくってみたい」と中村さん。杉並区政を近くで見守りながら、小さな夢を温めている。
中村涼夏(なかむら・すずか)
2001 年、鹿児島県指宿市生まれ。種子島などで幼少期を過ごし、名古屋市で育つ。鹿児島大水産学部卒。高校 3 年から約 2 年間、気候変動対策を訴える運動「フライデーズ・フォー・フューチャー」 のオーガナイザーを務めた。大学2年だった 21 年には、地球温暖化対策推進法改正案の参考人として国会に出席。同年の衆院選で、地元の立候補者に気候変動対策への考えを聞く「#選挙で聞きたい気候危機」プロジェクトを始めるなど、地方と国政をつなぐ活動にも取り組んだ。現在は、気候変動対策を 手がける NGO「ジャパン・クライメイト・アライアンス」ジュニアフェロー。超党派でつくる若者 団体「日本若者協議会」に出向し、政府の気候変動対策へ要望活動などを行っている。