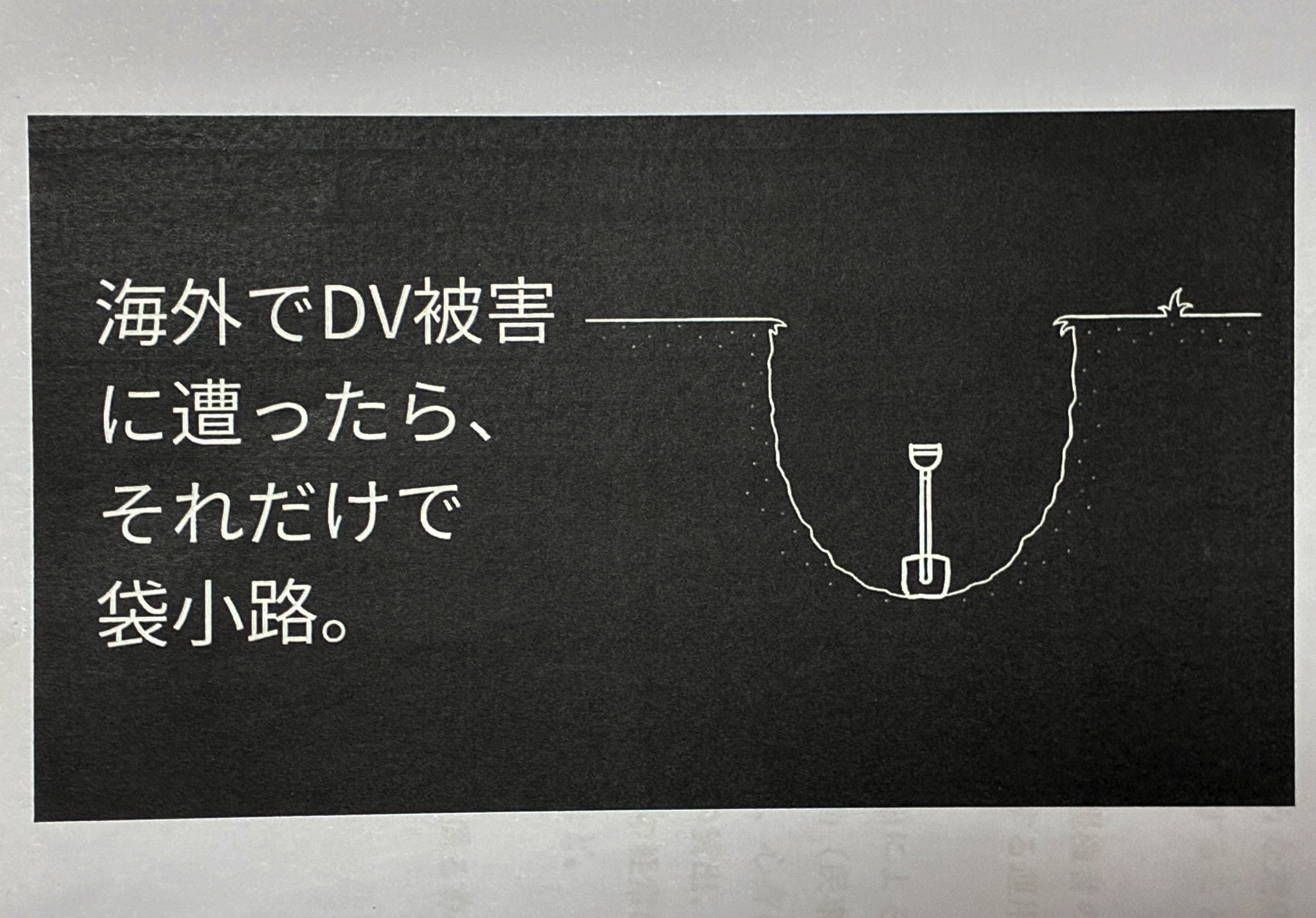今年1月、ハンガリーで日本人女性が元夫に殺されるという痛ましい事件が起きました。女性は2人の子どもと日本に帰国するため、子のパスポート発給について大使館に相談していました。子のパスポートは夫が持っており、離婚後共同親権で、夫の同意なく再発行できない状況でした。一方の親の同意を得ずに国外に子どもを連れ出すことを禁止するハーグ条約と、共同親権、DV被害への無理解が相まって起こった悲劇。4月16日、DV被害当事者、支援者らでつくる「ちょっと待って共同親権ネットワーク」が東京で集会を開き、再発防止に何が必要なのか、事件の背景をひもときました。
ハンガリー邦人女性殺害事件 ブタペストで2025年1月29日、火災があったアパートから日本人女性(43)の遺体が見つかった。防犯カメラの映像等から関与がわかり、アイルランド人の元夫が殺人容疑で逮捕・訴追された。女性はDV等を受けて婚姻関係が破綻し、2022年に長女を連れて帰国。長男は元夫が引き取った。元夫はハーグ条約に基づき、子の返還援助を外務省に申請。女性は長女とハンガリーに戻るが、2023年に離婚。元夫は別の女性と再婚し、オランダに在住していた。元夫が養育費を払わず、ハンガリーでの子ども2人との生活に行き詰まった女性は帰国を決意。しかし、元夫の同意が得られず、子のパスポートも取り上げられていた。女性は在ハンガリー日本国大使館に子のパスポートの再発行を再三懇願したが、共同親権者である元夫の同意が必要とされ、実現しなかった。
親権や後見人制度を扱う現地の専門機関が女性の相談・申告に対応し、今年3月には臨床心理士と子どもたちの面談が予定され、その後正式に帰国できる見込みとなっていたという。
現地の警察は謝罪、担当者を処分
事件後、女性の友人や弁護士の証言から、現地警察や公館の対応が不十分であったことが浮かび上がりました。女性は元夫から首絞めなどの暴行、銃の突きつけなどの脅迫、殺人予告、パソコンの窃盗、ネット上での嫌がらせ、養育費の不払いなどのDVを繰り返しうけていて、現地の警察にも被害を申告していましたが、取り合ってもらえませんでした。現地警察は事件後、女性の申告に適切な対応を取らなかったことを謝罪し、担当者6人を処分しました。
女性は日本公館に対しても、元夫からのDVを相談しましたが、公館は「警察に行くように」と勧めたのみで、子のパスポート再発行の要望についても「元夫の同意を取り付けるように」と女性に求めるなど、DVへの理解を欠いた対応を取り、女性を保護しませんでした。
事件は国会でも再三取り上げられましたが、外務省は「女性からDVについての具体的な相談はなかった」と答弁し、証言との矛盾が生じています。
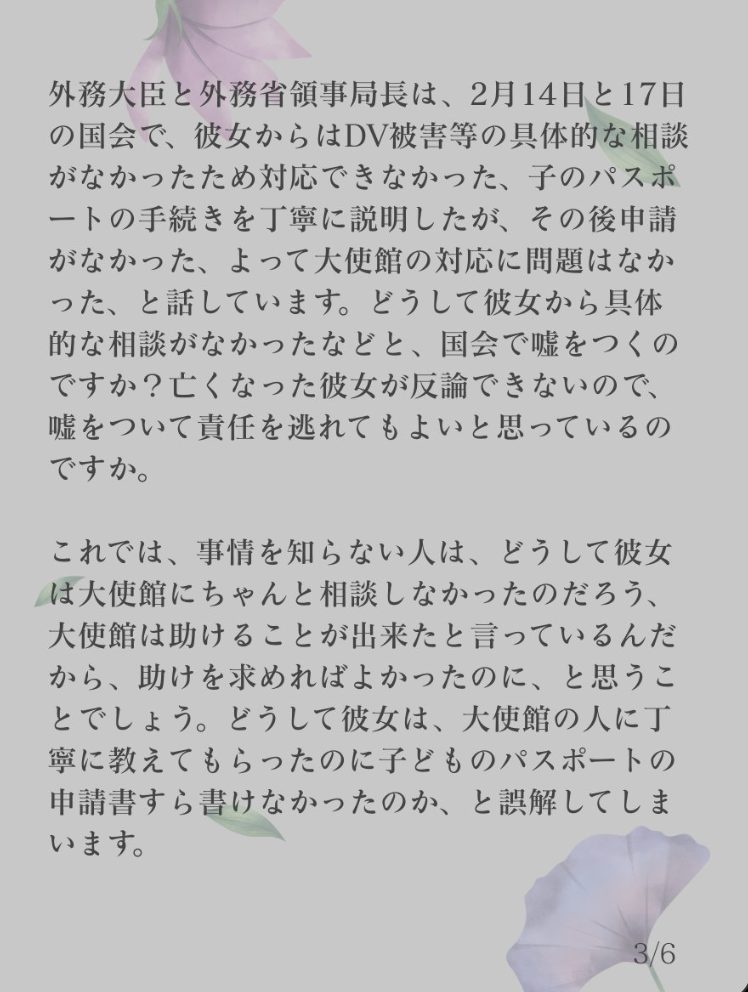
外務省「DVについての具体的な相談ない」
集会には外務省・海外法人安全課長とハーグ条約室長が参加し、「ちょっと待って共同親権ネットワーク」から事前に出された質問に回答しました。
主なやりとりは次の通りです。
Q)女性から大使館にどのような相談があったのか?
A)女性からの個別の相談の中身についてはプライバシーの観点から回答が難しい。DVについて具体的な相談はなかった。
Q)再発防止のために第三者を入れた検証をすべきではないか?
A)基本的に在外公館において業務を点検し、しかるべく対応してきている。

子のパスポートの発給「原則、両親の同意が必要」
Q)他方の親権者から同意が取れないことがあってもDV等の事情が疑われていて、子に必要がある場合、一人の親権者の同意によってパスポートを発給すべきではないか?
A)原則としては共同親権の場合、両方の同意が必要。状況に応じて一方の親権者の同意のみによって発給することができるという例外は、以前からルールとして持っている。その点について周知をしている。
Q)公館の短期貸出金をDV被害者にも適用すべきではないか?
A)短期貸出金は、短期旅行者が財布をすられたりカードをとられたりした時、宿泊代など当座の資金を、日本の家族や知人から送金してもらうまでの数日間に使ってもらうために貸し出す。日本までの航空旅費はこのお金では出していない。
Q)公館は現地の弁護士や支援団体の紹介、同行支援をすべきではないか?
A)警察署や弁護士に公館員が同行することはある。
外務省のDV専門家は非常勤で2名
Q)本省所属のDVの専門家とオンライン相談の便宜をはかるべきではないか?
A)本省の専門家は複数名(非常勤で2名)配置しているが、在外公館から相談があった場合に対応する。在外邦人から直接本省の専門家の意見を聞くことはできない。地域の事情を踏まえながら在外公館が相談を伺い、困っている点を明らかにした上で、本省の専門家にたずねるという体制をとっている。
Q)研修体制の充実は?
A)研修は非常に重要だと思っている。こういうことがあればDVと疑う、察知するということも研修で扱っていかなければならない。一方で、相談されている方々の個別のプライバシーへの配慮も極めて重要だと思っている。
親のDVは、子に対する「重大な危険」ではない?
Q)日本におけるハーグ条約の実施状況について。
A)ハーグ条約では子の利益が最も重要。子が外国に連れ去られた場合、子がもともと住んで慣れ親しんだ国に返すのが基本。返還が必ずしも子の幸せにならない場合もあるわけで、返還を拒否することができる事由も6点、定めている。
- 連れ去りから1年経過した後に返還の申し立てがされ、子が新たな環境に適応している
- 連れ去られた親が監護の権利を行使していなかった
- 申立人による事前の同意、事後の承認があった場合
- 返還によって子の心身に害悪を及ぼすこと、その他子を耐えがたい状況に置くことになる重大な危険があること
- 子の年齢に照らして、子の意見を考慮することが適当な場合で、子が返還を拒んでいる場合
- 子を返還することが基本原則により認められないこと。(返還先が紛争地帯など)
DVを理由とするものは4にあたり、「重大な危険」の有無を裁判所が判断。被害者側が証明しなければならない。あくまで子に対する危険であり、親から親へのDVはすなわち重大な危険とはなっていない。子の面前でのDVの場合は子への影響を考慮して重大な危険が認められる場合がある。
日本で返還拒否を裁判所が決定したのは49件中21件。このうちDVが理由のものは2件。
1件目は相手国がトルコ。父から母への暴力、父から子への性的な不適切な行為があった。子は父から母への暴力の巻き添えにもなった。
2件目はシンガポール。日常的なDVではないが、子の面前で父が母に暴力を加え、母が重傷を負った事例。
「外務省はDVを理解していない」
Q)DV被害が疑われる事例のフォローアップがどのように行われているか。
A)ハーグ条約の案件の当事者がDV被害を受けているかどうかを的確に把握することが極めて重要。DV被害が疑われる場合は、何よりも被害者に寄り添った対応が不可欠。
被害者にかかる情報の管理も徹底しなければならない。被害者の保護に知見を持つ専門家が外務省に配置されているので、助言協力を得ている。必要に応じてDV被害者に対し、住んでいる自治体の相談機関を紹介したり、支援員の情報を提供したりしている。在外公館との間で援助が決定された場合は連携をし、専門家の活用も行っている。もといた国に帰った後も、その国のDV被害者支援団体を紹介するなど継続的な支援を行っている。
質疑応答を聞き、福島瑞穂参議院議員は「DVについて具体的な相談がなかったというが、うそではないか? 『子どものパスポートが元夫に取られているから帰国できない』というこの相談自体がDVを示していると思う。外務省はDVを理解していない。本人が救済を求めて訴えてきたことにちゃんと対応しないのはプライバシーの問題ではないですよ」と質しました。
外務省海外邦人安全課は「旅券の申請にはさまざまな事情がある。夫の手許にあるというだけでDVを推認できるとは言えない」とし、「DVについての具体的な相談はなかった」と再度否定しました。
また、短期貸出金の対象については、中国・深圳での日本人児童殺害事件をめぐり、弁護士に無料相談できる仕組みが始まっていることなど、トラブルに対応するための費用として拡大を検討中、と補足がありました。
11カ国で日本語DV相談「ものすごい数、きている」
日本の専門家とオンラインで直接相談出来る体制について、ハーグ条約室は「国によって法律、制度、文化が違い、難しい。11カ国のDV被害者支援団体に日本語で相談が受けられる体制を作っている。ものすごい数の相談が来ている。中には深刻なケースもある。まずは現地の支援団体に対応していただき、在外公館がフォローアップしている」と話しました。
ハーグ条約は「子の移動を禁止する」ものではない
続いて外務省ハーグ条約室に勤務経験のある石井眞紀子弁護士が、今回の事件から見えてきたハーグ条約の課題について解説し、善後策を提案しました。

石井弁護士はハーグ条約のよくある誤解について、2点を挙げました。
・ハーグ条約は国際的な子の移動を禁止する条約ではない。16歳未満の子の監護に関する裁判をどの国でするのかを定めた条約である。
・ハーグ条約は子の連れ去りを違法だと定めた条約ではない。条約があるから絶対に子を連れて帰国できないというのは誤り。
石井弁護士は条約と現実の間に乖離があると話しました。その原因は2つあります。
- 1980年にできた条約であり、起草者らのDVへの問題意識が十分ではなかった。
- 主に想定されていたのは父親が自分に有利な裁判所で監護権の争いに勝とうとし、子を連れ去るケース。ところが実際は母親が国境を越えて子を移動したケースが大半だった。
共同親権の問題点を強化して加害者の道具に
「現状では、移民であり女性であるという二重のハンディを一切考慮していない条約だ。連れていった子を元の国に戻さなきゃいけないという単純な規定だが、性差別、言語の壁、就労できないなど経済上の問題が重なり、解決が難しくなっているケースが多い」
さらに、共同親権の問題も大きい、と指摘しました。
「どんな親であろうと、子は親の意向にさからって引っ越してはいけない。国境を越えてはいけない。それをするためには裁判所の許可がいる。そうした共同親権の問題点を強化して、DVや虐待の加害者の道具になっているのがハーグ条約です」
今回の事件の一番の問題点は、公館が子のパスポートを発行しなかったことだとし、「それは、母親をその国に閉じ込めておくことに等しい。なぜ公館は人を閉じ込めることにしたのか。女性が逃げる道を失ってしまったその判断がどのようになされたのか、疑問が残る。危機感が足りないのではないか」と問いました。
さらに、国連女性差別撤廃委員会から昨秋、日本の裁判官はジェンダーに基づく暴力に対する知見を深めてほしいと勧告を受けたことを引き合いに、「外務省や在外公館もどれほど理解しているか疑問。現場のDV被害者支援団体や弁護士の意見を聞いて理解を深めてほしい」と注文をつけました。
ハーグ条約で訴えられる監護者の84%が女性
DVから逃れるために子を連れて日本に帰国した結果、ハーグ条約を用いた法的・制度的暴力を受けた当事者らによる「ハーグ・マザーズ・ジャパン」のOさんがオンラインで現状を説明しました。
子連れで国際的な移動をして、ハーグ条約を使って訴えられる監護者の84%が女性。そのうち約75%がDVから自身と子を守るための避難だったといいます。
国連も「ハーグ条約がDV加害者から逃げる母子の出口を塞いでいる」と改善を勧告。条約を運用するハーグ国際私法会議(HCCH)も2024年6月、「DV被害者がハーグ条約を通じて更に加害行為を受けている」と認め、見直しの機運が高まっています。
こうした状況を受け、Oさんは「ハンガリー事件は氷山の一角」とし、海外に住む日本人のDV被害とハーグ条約に関する定量的なデータを収集・分析する第三者委員会の設置を求めました。
「海外で娘がDV被害に遭ってしまったら、子どもとうちに帰っておいで、と言ってあげられる国であってほしい。ハーグ条約を、被害者を守ってくれるものに変えてほしい」とOさんは訴えました。
父から子への虐待あっても「返還一択」
海外でDV被害と子への虐待があった当事者の動画メッセージも紹介されました。
「私は2012年に結婚、息子を守るために帰国し、誘拐だと言われている。息子はA国に帰るぐらいなら死ぬと言っている。父親の言動、存在そのものが、息子のパニックの原因になっている。父親は息子をなんども叩いて、暴言暴力を繰り返しました。息子は知的な遅れのない自閉症ですが、A国では治療も診断もうけられなかった。日本に来て、自閉症スペクトラムとADHDの診断がつき、すぐに療育を受けられるようになりました。ハーグ条約はDVから逃れた母子を再び暴力の危険にさらす道具となっています。どうか子どもの声を聴いてください。命がかかっています」
この女性を支援した「女のスペース・おん」の山崎菊乃さんが背景について説明しました。
A国では家族ビザでは働けない上、高コストの外国人は雇われない。そのため、女性と子どもには収入や生活の基盤が全くない状態だった。夫は育児に関わらず、現金を一切渡さないなどの経済的DV、暴言などがあった。子が3歳の頃から夫が子を叩くようになった。靴をぶつけたこともある。女性と子は2023年8月に、一時的な帰国として日本に戻り、子は自閉症スペクトラムという診断が初めてついた。同年12月に、夫がハーグ条約に基づく返還をA国に申し立てた。2024年1月に東京家裁でオンラインでの調停内裁判が始まった。女性は裁判官から「このケースでは子の返還一択」といわれ、判決ではなく調停合意を選択した。同年5月に返還の条件のためのADR(裁判外紛争解決手続)が始まり、子の主治医が「一緒に暮らすのであれば、日本に滞在して一緒に過ごす期間をつくり、子の同意を得てほしい」と申し出たが、夫は「できない」と拒否し、決裂。女性は事情変更の申し立てをしたが、2025年2月に、最高裁で棄却。一方、夫の人身保護請求が通り、今年7月に子を夫の国に戻すことが決まった。現在、女性と子どもは強制執行の恐怖にさらされている。
山崎さんは「家に執行官が来たことがあり、子はおねしょ、爪噛み、多動などの症状がひどくなった。いまは学校に行けない状態。子どもの福祉が本当にこれで守られているのか」と話しました。
DV被害者の恐れ、不安に触れる研修を
ちょっと待って共同親権ネットワークの副代表、斉藤秀樹弁護士は、共同親権導入を決めた法制審議会の議事録を紹介しました。

東京家裁所長代行の幹事は「DVが疑われる場合には、(家裁の)手続のどの段階においても優先的かつ慎重な検討がされていると思います」と繰り返しました。これに対し、ひとり親支援団体の委員がシングルマザーらにヒアリングすると「同じ国の出来事とは到底思えない」と返ってきました。家庭裁判所で面会交流などについて定める際には、DV被害者の訴えが認められにくいのが現状だからです。
斉藤さんは裁判官の研修について「民間への派遣型研修」を求めました。
「DV被害者支援、面会交流支援の現場で、被害者を支援し、加害者と連絡調整する中で、被害者が何を恐れ、何を不安に思っているのか、知ってほしい。DVという言葉が出る、出ないにかかわらず、恐れを肌で感じることが本当に大事だ。被害者が最初から『私はDV被害者』と言葉にすることはほとんどない。アンテナを研ぎ澄ましてほしい。外務省だけ、裁判官だけでなく、社会全体が身に付けるべきスキルだと思う」
DVを受けたら帰ってきていいと言える日本に
最後にちょっと待って共同親権ネットワークの代表世話人で和光大学教授の熊上崇さんがハンガリーの事件についてこう述べました。
「女性は日本への渡航ができれば命を失うことがなかった。多くの外国でDVを受けている方が直面している問題が明らかになった。ハーグ条約、子のパスポートの発給の問題が改善されなければならない。DVを受けたら逃げていい、帰ってきていいと言える日本にならないと行けない。彼女の死を無駄にしてはならない。私たちがその死を受け止めなければならないと思っている」