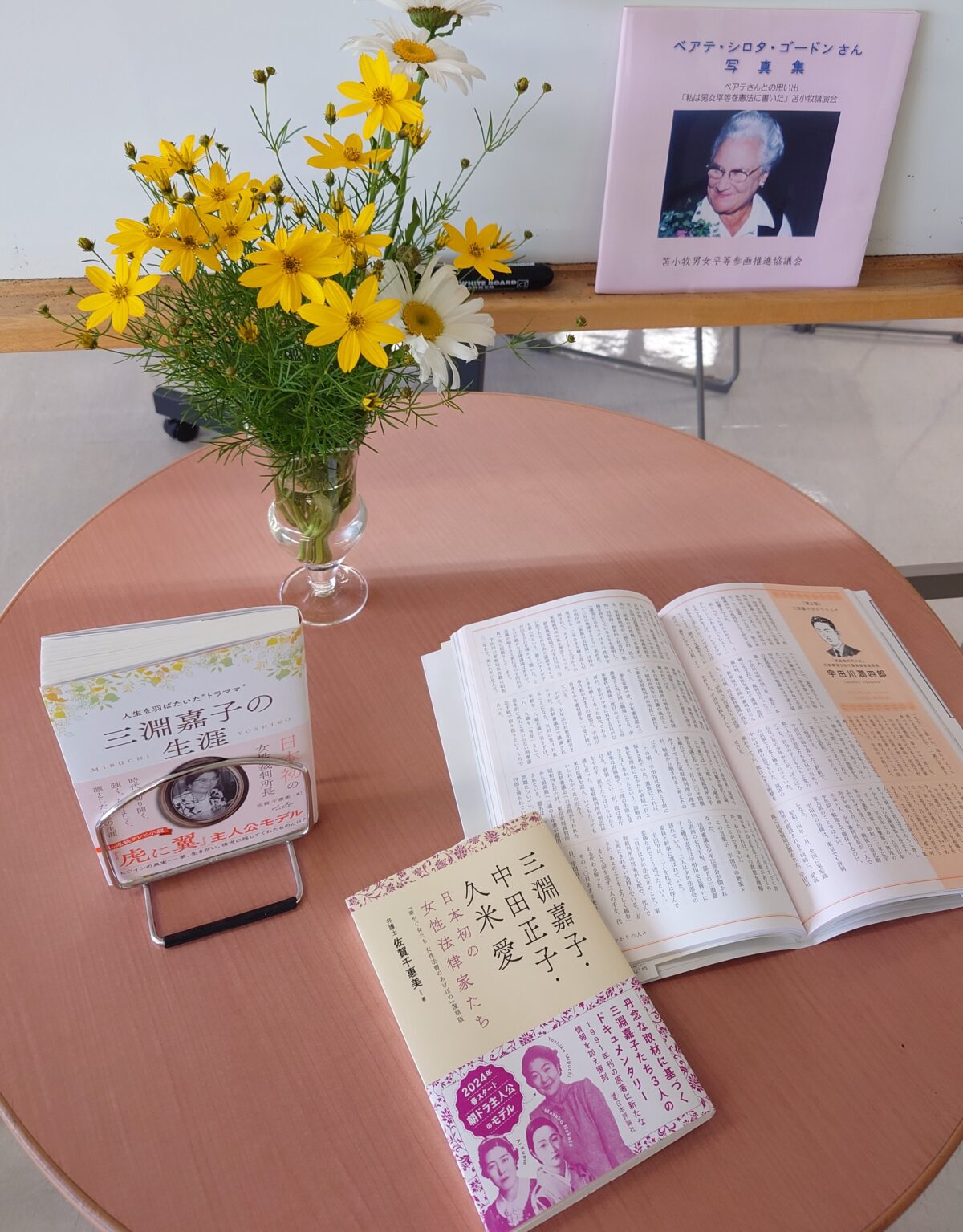なぜ、こんなに心を動かされるのだろう。NHKの連続テレビ小説「虎に翼」を見るたびに考えていました。これまで好きなドラマに抱いたものとは異なる感覚が湧いてきます。それは「味方になってくれている」という心強さのようなものです。
そう感じているのは自分だけではありませんでした。6月15日、秋田市の県中央男女共同参画センターで『朝ドラ「虎に翼」を語ろう!』というイベントがありました。20代から70代まで、女性を中心にさまざまな世代の人たちが集まり、ドラマを通して感じ考えたことを熱く語り合いました。
同性への強い思いは
15人ほどが参加したイベントは「恋愛」について考えるところから始まりました。
「寅子(伊藤沙莉)と花岡(岩田剛典)が恋愛関係だということに自分はずっと気づかなかった」と参加者の一人が言いました。「私は自然に(恋愛感情を)感じ取りました」「お互いを尊敬し合っている関係でしたよね」という声のほか「私は恋愛をからめてほしくないなあ、と思いながら見ていました」というつぶやきもありました。
寅子と花岡の関係性から、話題は轟(戸塚純貴)の花岡への思いに移り、ある参加者が次のように語りました。
「強い思いというのが異性相手だったら『恋愛』だと思われるのに、轟さんと花岡さんについては『勝手に同性愛に結び付けるな』みたいな意見が出ていたりして、すごく、もやもやしました。同じ気持ちであっても、相手が同性か異性かで周りの見る目がこんなにも変わるんだなって。轟さんのように、同性への強い思いが恋愛なのかどうなのか分からなくて悩んでいる当事者は多いのに『ないもの』にされてしまうのは嫌だなと思いました」
別の参加者は「同性で恋愛関係になるっていうモデルが周りになさすぎるんだと思う。自分の気持ちをどこに当てはめたらいいのかという足がかりが、なさすぎる」と話しました。
ちなみに脚本家の吉田恵里香さんはSNSで〈轟の、花岡への想いは初登場の時から【恋愛的感情を含んでいる】として描いていて私の中で一貫しています(本人は無自覚でも)〉と発信していました。
戦前戦後が舞台のはずなのに
「この脚本を書いている人はすごいなと思います」「今の時代に通じるものがありますよね」「戦前戦後の話なのに、今の時代の話なの?って」
戦前戦後の話なのに今に通じる―それは、悲しいことでもあります。
「憲法で男女平等といくら言っても、長い間の家父長制の慣習っていうのはもう、染み付いているから、抜けない感じがします。(明治民法が定めていた)女性は無能だというのも、戦後だってやっぱりそういう扱いをされてきたから。職場では女性はお茶くみだし、女性は車で通勤しちゃいけないと言われたこともありますし、女性は運転が下手だとけなされることもある。こういうのがいまだにあることが、ドラマの人気の秘密だと思います」
「私の話を遮らないでほしい」
ある女性が語りました。
「最近新聞で見たんですけれども、マンスプレイニングっていうんですか、私は初めて知った言葉だったんですが、その意味は『男性が女性や子どもに対して、見下したような、自信過剰な、しかししばしば不正確な方法でコメントしたり説明したりする』とありました。そういう場面がドラマのいたるところにあったなあと。そして今も実際、見ることがあります」「男性が優位、男性が上という意識がどこかにありますよね」
穂高先生(小林薫)の一言に救われたという声もありました。
「教室で意見を言った寅子に、穂高先生が『続けて』と言う場面がありました。私の言葉を最後まで聞いてくれる人はいなかった、ということを寅子は言っていたと思うんですが、その言葉が私はすごく印象に残っていて」「女性は無能力者という言葉が教室から聞こえてきて、寅子が『はて?』と言うシーンですよね」
話そうとすると言葉を遮られ、時に否定される。言いたいことは言えず、一方でマンスプレイニングに遭う―。そういう経験について、皆さん「あるある」と共感していました。
芽を摘んできたのは誰なのか
「お母さん(石田ゆり子)のせりふもよかったです。『女の可能性の芽を摘んできたのは誰なの、男でしょう』っていう」「寅ちゃんが弁護士になったときの『男女関係なく!』という締めの言葉が、すごく、ぐっときました」「かっこよかった」
男女関係なく、と言い切る寅子の言葉が深く響くのは「現実はまだまだそうではないからだ」という声もありました。
「同等の能力の男の人と女の人がいて、どっちを出世させるかとなったら、やっぱり男の人を出世させていますよね」「私の職場では『家族を養わなきゃいけないだろうから』と言って男性を昇進させていました。明らかに能力が高くても女の人は役職に就けないということが本当にあって」「はて?だよね」「男の人は、下駄を履かされていると思います」

男性も女性も苦しめられる
下駄を履かされて苦しむ男性もいるのではないか、という意見もありました。
「若い男性職員のなかには、下駄を履かされてよかったと思う人もいるかもしれないけれど『男はそうならなければならない』という責任を感じてしまって、自分らしく生きられなくて苦しむ人もいる。それをまるで無視して『今までこうだったから』と続けてしまう。そういう慣例を断ち切らないと変わらないと思いました」
「必ず世帯主が家族を養うっていう構造や発想も問題だと思っていて。結婚したくてもできない人が増えている理由の一つも、養えないぐらい賃金が低くなっていることがあると思う。会社が要求する仕事の量も質も無駄に高まっていて、若い人が少なくなっているのに、50、60代の人が若い時は複数で分担していた仕事を1人にやらせたりしている」
「労働者としての人の価値をどんどん下げられて、替えがきくようにと非正規雇用を増やされている中で、女性は『家庭のこともあるし』とかいろいろ理由をつけて、使い勝手のいい労働力として細切れにされている」「寅ちゃんの弟の直明(三山凌輝)が『自分が大黒柱になる』って言ったときに、花江ちゃん(森田望智)が『みんなが大黒柱になればいいんじゃない』って言っていた、あの考え方がいいですよね」
別姓で家族の団結が崩れる?
大黒柱について考えるうち、話題は「結婚後の姓」に移っていきました。
「男性が女性の名字に変えるとなると、親戚縁者の了解を得て、中には反対する人もいて、すごくもめたという話を聞いたことがあります」「夫婦が同じ名字でなければいけないのって世界で日本だけなんですよね。別姓が選べるようになると『家族の団結が崩れる』とか自民党の一部の人たちが言っていますけど、じゃあほかの国で家族が壊れたり混乱してるんでしょうかね」「その事例、出してみなさいよってテレビに向かってときどき言ってます、私」「別姓も選べるようにしてほしいって言っているだけなのにね」
ちなみに日本では、夫婦のうち「夫の姓」を選択する割合は約95%というデータがあります。
「男なんだから」という規範
明治民法の「家制度」のもとでは、結婚は「家」を存続させるためのものであり、結婚の決定は家長(戸主)が握っていました。しかし戦後の1947年、民法改正によって家制度は廃止されました。
結婚について、憲法には次のように記されています。
日本国憲法第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
ただ「家意識」は令和のいまも根強く、妻の姓を名乗ることを「下」に見るかのような風潮がある、という声もありました。
「長女の私は両親から『あんたが婿を取るんだ、あんたは婿取りだ』『長男と結婚したらダメだ』ということをずっと言われてきました。けれど『あんたは婿取りだ』と言っていた親族が、他家の婿さんに対しては『婿だどよ(婿だってよ)』みたいにせせら笑う感じでうわさ話をしている。そういうのがすごく嫌でした。もしかすると妻の名字になる男性に対して、男性の社会あるいは女性の社会からも『あってはならないこと』みたいな反応が、今もあるんじゃないかなって。男なんだから嫁を取るべきだ、みたいな規範があって、そうでないケースはイレギュラーだという考え方がどこかにあるのでは」
そういえば秋田では「本家」「分家」というワードによく出くわします。
「こんなに憲法を読んだことはなかった」
「虎に翼」は憲法や法を正面から扱っています。
「皆さん今まで、日常で憲法なんて見ていましたか。見ることがなかったですよね」「憲法自体、学校でちゃんと習わなかった気がします」「項目は一通り習ったけど」との声もありました。
寅子の上司である多岐川(滝藤賢一)が、花岡の死を思いながらこう語りました。
「人間、生きてこそだ。国や法、人間が定めたもんはあっという間にひっくり返る。ひっくり返るもんのために、死んじゃあならんのだ」。その言葉に「心を打たれた」という声が多数ありました。
「裁判所とか弁護士さんとか、自分には関係ないことだと思っていました。裁判所なんてもう、遠い遠い、関係ないものだと。でも法律って本来は多岐川さんが言う通りのものだなと思いました。私が若いときは、セクハラやパワハラが本当に日常茶飯事で、だけどそういう言葉も法律もなくて。時代は少しずつ変わってきたと思います。でも、よくなってきたはずなのに、若い人たちがいま本当につらそうだなということも感じます」
なぜケア労働の賃金は低いのか
社会はよくなってきたのだろうか。変わってきたのだろうか。この問いかけに、ある参加者は「ケア労働(介護士や保育士など)の賃金がずっと低いままなのが気になる」という話をしました。
「介護職って、男女の賃金格差が割と少ないと言われているんですけど、それは単に男性の賃金も低いからだと思います。ケア労働は昔から女性の役割で、家で無償でやってもらえるものだったことが、職業になった今もずっと尾を引いてるんだなと。家のことは女がやるものだ、それに対して金を払うもんじゃないっていう年配のお父さんたちがまだ多いと感じます。お母さんのほうも、ケアを務めるのが自分の役割だと思っているから、それを不幸だとは思っていない。そういうのを見聞きすると、悲しいと思ってしまいます」
「働いて、子どもも産め、家事はもちろん介護もしろ…女の人はやることが多すぎます。昭和世代の男の人は働いて帰ってくればテーブルに座って、ご飯を食べて、風呂入って寝るだけ。でも女の人は作って、片付けて、洗濯物をたたんで風呂のことをやって…」「夫からありがとうと言われることはないです。男の人は買い物とか何かやったりすると『お父さん、ありがとう』って言われますけど」
女は座っていられない
話題は、猪爪家の食卓の風景から「女性の座る場所」へと膨らんでいきました。
「昔は女の人の食事は男の人とは別、みたいなことがあったと思いますけど、今はもうないですかね?」「お葬式などのときは、男性陣は一人一人にお膳がついて、女性陣は一つのテーブルでまとめてオードブルみたいなものを食べる、というのは今もあります」「テーブルがあるだけいいかも。お葬式の手伝いに行くと女性たちは立って食べますから」「そういうときに座ってると『あそこの嫁だば座ってだっけ』って言われるしね」
声を上げることのできない人を思う
声を上げられる人もいれば、上げることのできない人もいる。そこをきちんと描いてくれたことが心強かった、という意見がありました。
「立ち上がれる人、闘える人ばかりじゃない。それを盛り込んでくれたことがうれしかったです」「社会は女を無知で愚かなままにしようとしているという話のときに『闘わないのは愚かだ』ということを、よねさん(土居志央梨)が言ったんですよね。それに対して、弱音を吐く人をそのまま受け入れられる弁護士になりたい、というようなことを寅ちゃんが言っていたと思います」
「忙しくて時間がないとか、声を上げる気力も余裕もないから声を上げられないという人たちもたくさんいると思います。それを『声を上げないのが悪い』みたいに言われると、ちょっとしんどいなと思う。政治の世界に女性が入っていけないのも、そういうことだと思います。だから闘いたくても闘えない女性もいると描いてくれたことに、すごく共感します」「勉強する機会があることすら知らない人もいる、っていうせりふもよかったですよね」
主題歌にも自分を重ねる
米津玄師さんの主題歌「さよーならまたいつか!」の歌詞に重ねて「私も、春がどこから来たかわからないまま大人になった感じです」と話す女性もいました。
「ただただ野山で遊んでいるだけの子どもだったので、仕事を持つとか、自分で生きていくとか、そういう情報を持っていなかった。何も、分からなかったなあと」
「オープニングのアニメも、そういう格差をあえて表しているように感じました。例えばリヤカーで柴を引いてる女性と、本を読んでる女性は、情報格差があって、そういう中で『女はこうして生きなきゃ』みたいなことを押し付けられたら、どうなっていくのかなって」
なぜこの物語に、こんなにも惹かれるのか。ある女性は「世の中が変わってないからじゃないか」とつぶやきました。
構造的な格差を見つめる
女性、男性ではなく「人間性が大事」という声もありました。
一方で、日本社会には男女の賃金格差や家事時間の差など構造的な男女の格差が存在します。
「男性が上という構造が社会には確かにあって。そこを見て見ぬふりをせずに変えていかないと、平等にはなっていかないですよね」
女性が政治から遠ざけられている、という声もありました。
「選挙のことは父さん(夫)の意見を聞かなきゃいけない、と話す女性もいます」「夫が『うちには4票ある』と言って、妻と子の票は『俺のもの』として数えてしまう」「0歳から選挙権を与えて、親が行使すると大阪府知事が言っていましたけど、同じような発想ですよね」
「私たちには力がある」
秋田には和崎ハルという人がいます。1946年、秋田県で初めて代議士になった女性です。
「戦後、普通選挙で女性議員が39人誕生して、憲法はその後につくられたんだそうです。つまり女性議員がちゃんと憲法をつくる場に携わっていた。女性は、自分たちにはそういう力はないんだって思いこまされているし、個々バラバラに分断されてるところがすごくあると思います。でも自分たちで変えていけるという実績があったことは、もっと知られていいと思う。それぞれの生活の中でできることが人それぞれにあって、そこからちょこっとずつでも、変えていけたらいいのかなと思います」

安心して話せる場がほしい
いま、どんなことを望んでいるか。ある女性は「自分の意見を最後まできちんと聞いてもらいたい。そういうことが大切だと思う」と話しました。「意見を言うと(男性から)『言い訳するな』とか、言われますよね」との声も。女性たちが安心して話し合える公の場は、まだまだ、足りないのかもしれません。
共有し、つながるために
県中央男女共同参画センターの佐藤加代子さんは、今回「語る会」を開いた理由を次のように語ります。
「このドラマが始まったとき、寅ちゃんが新聞を読んでいましたよね。そこで目にしたのは新しく公布された憲法の、第14条でした」
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
「このシーンでドラマが始まったとき、じわっと涙があふれました。こんなドラマがあるのかって。このドラマは、本当に女性たちが戦前に置かれていた現実―結婚して子どもを産んで、よい妻であり、よい母であり、そして明治民法のもとで無能力者とされた現実や、社会的に差別された存在だったことを描いています。戦後、憲法ができて、その中には(法の下の平等をうたった)14条もあれば(両性の本質的平等をうたった)24条もあって、男女平等がきちんと書かれたものを私たちは持っているんだということを、ドラマを通して改めて認識しました。これはやっぱり、みんなでもっとわいわい喋りあって、お互いに『こんなことを思ってる』『あのシーンはよかったね』と共有したいなというのが企画した理由です」
「この会をまたやってほしい」という声が参加者たちから上がり、「虎に翼」を語る会は2回目の開催が決まりました。
〈参考資料〉
・吉田恵里香さんX https://x.com/yorikoko
・「法律情報基盤」(SANO Tomoya 名古屋大学大学院法学研究科)https://law-platform.jp/table/129089d/5
・法務省サイト https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
・内閣府男女共同参画局サイト
・東京新聞TOKYO Web <視点>選択的夫婦別姓 自民の一部議員の反対で女性活躍の阻害に (2024年3月27日) https://www.tokyo-np.co.jp/article/317546
・東京新聞TOKYO Web 「ゼロ歳児にも選挙権」吉村洋文・大阪府知事の真の狙いは? 識者は「新たな不平等を生む」と指摘 (2024年5月16日)https://www.tokyo-np.co.jp/article/327333
・秋田県立博物館 アキハクコレクション https://www.akihaku.jp/digital/collection/contents.php?serial_no=172&category=8&lang=