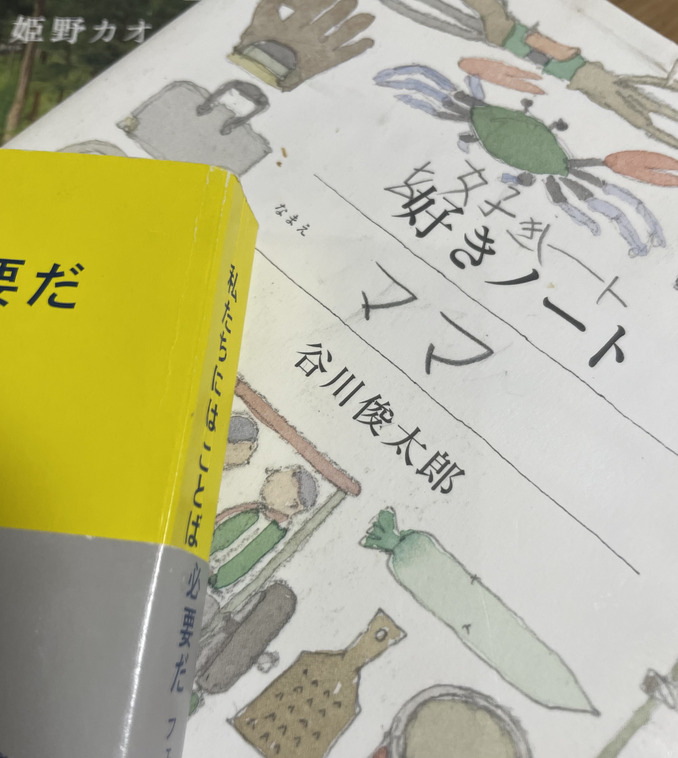この国で生活していると、名前にまつわるモヤモヤが尽きない。家制度はとうになくなったのに、「嫁」「婿」「主人」「家内」などの呼び方を耳にするし、これまで国連の女性差別撤廃委員会が3度にわたって勧告しても、夫婦同姓を義務付けた民法の規定は変わっていない。10日、経団連がとうとう選択的夫婦別姓の導入を政府に提言した。それでも岸田文雄首相は慎重な姿勢を崩していない。「ジェンダー平等後進国」と言われるはずだ。
少し前には、その岸田首相の妻・裕子さんが、春の園遊会に出席した際の「名札」がニュースになっていた。裕子さんが胸元につけた名札は「岸田文雄夫人」で、名前はない。「男性の付属物ってこと?」「人権意識はどうなっているのか」「家父長制が色濃く残っている」―。SNSでは様々な批判が飛び交った。想像してみてほしい。もし自分が同じように名前を消されたら、どんな気持ちがするだろう。公的な場でさえ「夫人」という役割のみが強調され、個人を表す名では呼ばれない。まずは名前を記し、その上で関係性を表記するといった対応は取れなかったのだろうか。
関係性が重んじられ、いつの間にか「個」はどこかに消えてしまう。子の親になり、周りのママ友や保育園の先生たちから当たり前のように、「○○ちゃんちのママ」と呼ばれるようになった時、ちょっとした寂しさと戸惑いを感じたものだ。私がどういう人間かよりも、「ママであれ」と社会的な役割を押しつけられ、逃げられなくなったような気がした。
遠い親戚の女性から、名のない手紙を受け取った時の衝撃も忘れられない。女性の夫の名前はフルネームで記されていたのに、筆者である彼女自身の名前が見当たらない。便せんの隅に、夫の代筆であることを表す「内」という文字が小さく書かれていただけ。さらさらと流れるように美しい文字で、丁寧な言葉遣いで、季節の挨拶とともに私の体調を気遣うその文面は、私が知る女性そのものだった。それなのに、彼女は「影」になっていた。とても驚いたと同時に、女性が名前を失っていたことが悔しかった。「家」に従属しているように感じたからだ。
名前は人格権の象徴だ。でも、なかなか伝わらない。日本は世界で唯一、民法で夫婦同姓を義務付けられている。法相の諮問機関である「法制審議会」は1996年に選択的夫婦別姓の導入を答申したが、保守系議員が「家族の一体感が失われる」などと反対しており、ずっと実現していない。
銀行口座、カード、パスポート、免許証・・・。改姓は手間もコストもかかる「生活上の困りごと」だ。結婚した夫婦のうち妻が改姓するケースが9割に上り、改姓の負担は女性に偏っている現状は間接差別だと言われている。愛着のある名前を失って心を痛めた人も多いだろう。旧姓の通称使用では、契約などでトラブルもあり、国際的なビジネスシーンでは通用しないし、キャリアの断絶にもつながっている。企業にとってもリスクになる。そんな中で、ビジネスリーダーたちが選択的夫婦別姓の導入を政府に提言したことの意味はとても大きい。現行法の規定による経済活動への支障の数々は、改正に向けた重要な理由付けとなることは言うまでもない。
でもその前に、自分の一生を形作る軸である名前の決定権を、誰かに奪われたくないというシンプルな願いが、なぜこの国では大切にされないのか。私たちは「夫人」「ママ」である前に、「わたし」だ。名前の強制変更で生み出す「一体感」って何だろう。望む姓が夫婦で違っていても、同じ姓だとしても、自分たちで選びとりたい。「個」をないがしろにし、多様性に欠いたままの社会は恐ろしく脆いと思う。
名前のことを考える時にいつも思い浮かぶのが、映画「千と千尋の神隠し」の1シーンだ。湯婆婆に名前を奪われていたハクは、千尋のおかげでとうとう自分の名前を思い出す。その瞬間、体から鱗のようなものがはがれ、はらはらと宙に舞う。ハクは千尋とともに述懐する。川の主であったこと。溺れかけた千尋を救おうとしたこと。名前とともに、自分がどんな人間(この場合は神様?)だったのかという記憶もいっぺんに取り戻していた。
映画の公開は2001年、既に四半世紀近くが過ぎた。私たちの尊厳はいつ取り戻されるだろうか。