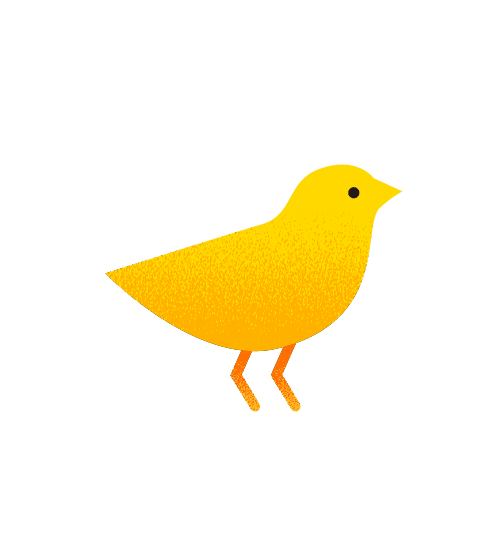今年8月で太平洋戦争の終結から80年を迎えます。
日本政府は民間人の戦争被害者に対する補償をこれまで一切行っていません。戦後、日本国籍を失った台湾、朝鮮半島出身の元BC級戦犯、シベリア抑留者が求める謝罪・補償にも応じていません。一方、軍人とその遺族には恩給や遺族年金による補償があります。こうした「官民格差」「内外格差」の是正を求め4月18日、4団体が東京都内で共同記者会見を開きました。
空襲被害者救済阻む「受忍論」
日中戦争開戦(1937年)から太平洋戦争の終結(1945年)までの日本人の死者は310万人。そのうち80万人が民間人です。米軍機の本土空襲により亡くなった人は50万人を数えます。しかし一部の被害者を除き、被害への補償はなされていません。国が補償を拒む背景には、1968年に最高裁判決が示した「戦争被害受忍論」があります。「戦争は国の存亡を懸けた非常事態で、受けた被害は国民が等しく受け入れなければならず、国家は補償義務を負わない」とする考え方です。

戦後80年の節目に、この「受忍論」を超えようと、超党派の国会議員連盟(空襲議連、平沢勝栄会長)は昨年秋、空襲で障害を負った生存者に一時金50万円を支払うとする「特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案」のたたき台を作成しました。法案には、国が空襲等による被害実態を調査することや、追悼事業を行うことなども盛り込まれています。今年3月の参議院予算委員会で、石破茂首相は「(空襲被害者の)意見をきちんと聞いて、次の世代に対する責任として行政が判断しなければならない問題」と答弁しました。しかし厚生労働省は「対象者が見込みより増える恐れがある」「過去の政府の対応と整合性が取れない」などと反発。与党内の調整が付かず、法案提出の目処が立っていません。
遺族「対象外の悔しさ、飲んだのに」
法案では遺族は補償の対象外となっています。遺族の一人で、東京大空襲で母と弟2人を失った河合節子さん(86)は「本音を言えば悔しい。でも、この案を飲んだんです。戦後80年の今年、民間人の空襲被害に対する救済法をぜひ実現してほしい」と語りました。
「最大の犠牲者は、言うまでもなく死者です。残された遺族、中でも幼くして孤児になった人も給付の対象ではありません。それでも、この法案の成立を望んでいるのは、空襲被害の実態調査をしてほしいからです。このまま民間人の空襲犠牲者をうやむやにしたまま、闇に葬ることは許されません」

そしてこれは、過去の話ではない、と河合さんは警鐘を鳴らします。
「もしも私たちのこのささやかな要求さえも拒否されるのであれば、近い将来、発生するかもしれない民間人の戦争被害も、受忍を強いられることになると恐れています。既に政府は、民間人被害を想定して、シェルター建設や先島諸島、沖縄などからの避難方法を検討しています」
戦時中には民間人を対象にした「戦時災害保護法」がありましたが、戦後、日本を占領したGHQ(連合国軍総司令部)により廃止されました。同時に廃止された軍人恩給だけが、1953年に復活しています。
河合さんは問いかけました。
「受忍論が生まれたのは、人権、平等を重んじる現憲法下なのです。今の憲法の下で作られてしまった受忍論をみなさん、どう思われますか?」
兵士以外にも戦争PTSD
1944年のサイパンやフィリピンでの日米地上戦(南洋戦)で、沖縄出身者の住民8万人のうち2万5000人が死亡し、1万7000人が負傷しました。続く1945年の沖縄戦では、当時の県民60万人のうち15万人が戦死しました。このうち、戦闘参加者と認定されなかった民間人戦死者7万人に対しては、未だに国からの謝罪も補償もありません。
沖縄戦の被害者は2012年、南洋戦の被害者は2013年に国家賠償請求訴訟を起こしました。高裁判決では日本軍による傷害や住民のPTSD(心的外傷後ストレス障害)が認定されたものの、沖縄戦訴訟は2018年、南洋戦訴訟は2019年、最高裁判決で住民敗訴が確定しました。判決は旧憲法には国家賠償の規定がないなどとする「国家無答責」の立場に立っています。

これらの裁判を戦ってきた民間戦争被害の補償を実現する沖縄県民の会の顧問弁護団長、瑞慶山(ずけやま)茂さんは「戦争PTSDに改めて注目を」と訴えました。
沖縄戦訴訟では原告79人中43人(認定率54%)、南洋戦訴訟では原告45人中28人(認定率62%)に、戦争PTSDが認められました。PTSDの影響は、戦後も家庭内暴力など世代間を超えて深刻な被害として引き継がれました。戦後80年経って、子世代が親の戦争PTSDを知り、初めて自分の生育歴に被害が及んでいたと気づくこともあります。
旧日本兵のPTSDについては、厚労省が2024年度に陸軍病院などに残されたカルテ、関連文書、体験記などを収集し、調査。今年7〜10月に、東京都千代田区の戦傷病者史料館「しょうけい館」で企画展が予定されています。
瑞慶山さんは「民間人にも多数の戦争PTSD被害者がいるはず。民間人についても直ちに調査を実施すべきだ」と国に要求しました。そして、民間人戦争被害者救済法の早期制定も求めました。
旧植民地出身者を「国籍」で除外
日本軍の指示の下、南方で捕虜監視員などとして働いた朝鮮半島・台湾出身の青年らは、戦後、連合国側が開いた軍事裁判でBC級戦犯として処罰されました。有罪となったのは321人、うち44人が死刑となりました。さらに1951年に締結されたサンフランシスコ講和会議の対日平和条約で日本国籍を失い、旧日本兵や遺族に対する補償の枠組みから排除されてきました。
1955年に東京・巣鴨刑務所で韓国・朝鮮人のBC級戦犯者らが結成した「同進会」が、国家補償を求めて日本国政府に要求を続けてきました。1991年に日本政府を相手取り、国家賠償請求訴訟を起こしました。1999年に敗訴が確定しましたが、東京地裁、東京高裁、最高裁のいずれも事実は認定し、「立法府の裁量的判断に委ねられる」と指摘しました。運動の中心人物だった李鶴来(リ・ハンネ)さんは2021年3月、96歳で亡くなりました。

運動を引き継いだ朴來洪(パク・ネホン)会長は元戦犯の2世。李さんら1世の功績を「本当に立派な方々だった。植民地にされ、よくわからない状態で、東南アジア、ジャワ等に行かされて捕虜の監視をし、原告不在の裁判で有罪に。その後も自分たちに罪をかぶせた日本に住み、知人も親戚もいない中で、同じ朝鮮籍の仲間と歩んできた」と振り返りました。
「都合がいいときは日本人、都合が悪くなると朝鮮人」
しかし、李さんが生前、歴代首相に出した33回の要望書が実現されることはありませんでした。韓国政府は2006年、元BC級戦犯らを「植民地支配の被害者」と認め、その名誉を回復しています。一方、日本政府は日本国籍がない人への補償はできないとの立場を変えていません。
朴さんは「都合がいいときは日本人、都合が悪くなると朝鮮人。その言葉を浴びせられてきた1世のことを思うと悔しくてたまりません。このまま立法が実現できなければ、それは日本の人たちの恥ではないでしょうか? 日本は平和国家とマスコミやネットで出ているが、それは本当なんでしょうか?」と問いかけました。
シベリア抑留者にも「国籍の壁」
戦後、旧ソ連に抑留され、シベリアで強制労働を課せられた人たちへの補償も十分ではありません。シベリア抑留経験者支援センターの西倉勝さん(99)は、「60万人いた仲間のほとんどが鬼籍に入り、こうしてお話できるものは、本当にわずかになりました。だからこそ、亡くなった仲間たちに代わってしっかり言うべきことを申し上げなければならないとやって参りました」と切り出しました。
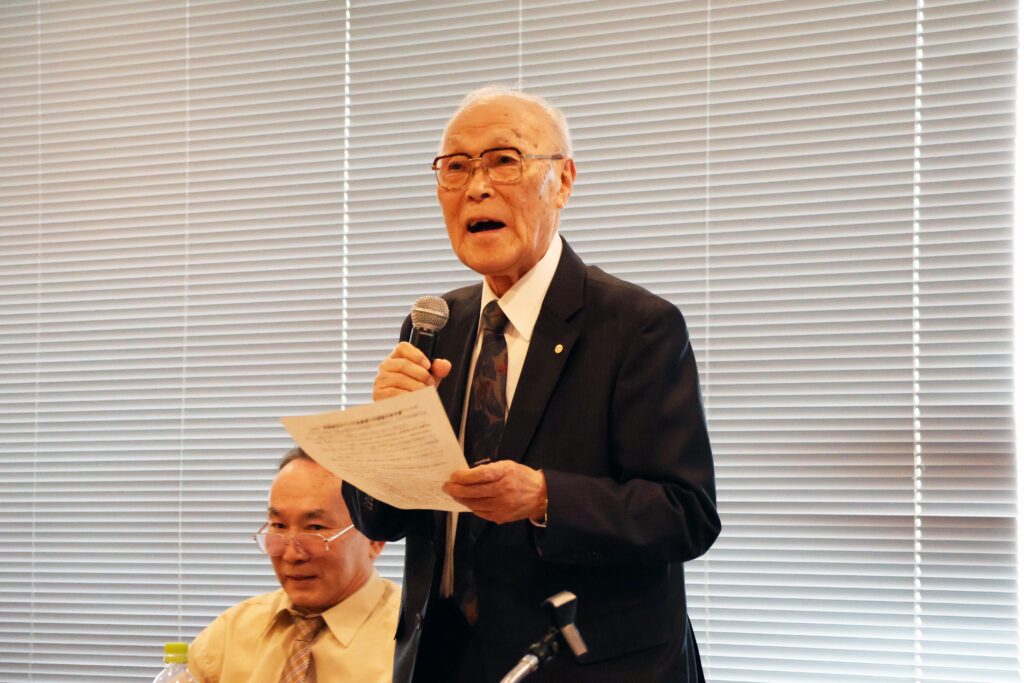
西倉さんは20歳の時、陸軍歩兵として朝鮮半島、満州、旧ソ連国境に派遣され、終戦後は樺太に近いコムソモリスク収容所に連行され、3年間、極寒の地で強制労働に従事させられました。抑留者は帰国後も「共産主義者」「アカ」とのレッテルを貼られ、就職や生活に苦労した人が多かったそうです。
1956年の日ソ共同宣言で日本とソ連は互いの賠償請求権を放棄すると定めたため、抑留経験者は補償を日本政府に求めるしかなくなりました。国家賠償請求訴訟は原告(抑留経験者)側の敗訴に終わりましたが、1997年の最高裁判決は、補償の要否について、「国家財政、社会経済、戦争によって蒙った国民の被害の内容、程度等に関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断に委ねられたものと解するのが相当である」としました。
2010年に戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(シベリア特措法)が議員立法で成立し、抑留経験者のうち生存者6万9000人に25万円〜150万円の特別給付金が支払われました。しかし、それでは不十分だと、西倉さんは言います。
「いまだに、いったい全体で何人が拉致され、抑留され、亡くなったのかわかっていない。硫黄島の死者の3倍もの人が、戦闘もしていないのに亡くなっているのです。朝鮮戦争やベトナム戦争の米軍の死者より多いのです。ふわっと、約6万人とせず、もっと真剣に、本気で調査すべきです」
そしてここにもBC級戦犯と同じ「国籍の壁」があると指摘しました。
「1945年8月まで台湾・朝鮮は日本の植民地で、みなさん全員『日本人』でした。一緒にシベリアに拉致され、強制労働をさせられ、無事に帰られた方々もそれぞれ苦労して戦後を生きてきました。それなのに、特別給付金を払わない。国籍条項で除外する。これはなんとかしないといけません。速やかな立法を求めます」
「日本が国際人道法を守る先頭に」
話は現代にも及びました。ウクライナやスーダンやガザで続く戦闘において、捕虜への虐待や国際人道法に違反する虐殺が起きていることに触れ、西倉さんは訴えました。
「抑留の被害国である日本が国際人道を厳格に守るように強力に世界に訴え、国際司法裁判所や国際刑事裁判所の活動を全面的に支えるべきです」。

最後にシベリア抑留者支援・記録センターの代表世話人、有光健さんが四つの立場をつなぐ視点として次のように語りました。
「日本の戦後処理、戦後補償、援護政策は民間人が基本的に排除され、官民の格差がものすごく大きい。国籍条項によって、原爆の被爆者援護法以外はすべて外国籍の人が除かれている。内外格差があります。その2つを是正しなければいけない」
広がる格差 軍人遺族に特別弔慰金積み増し
4団体はこの日の共同アピールで官民格差について具体的に記しました。
<2025年予算成立と同時に、約57万人の軍人・軍属の戦没者の遺族(子や父母、きょうだい、孫ら)に各55万円の記名国債で、10年間で総額3135億円を追加支給する『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法』改正案が、全会派一致で可決・成立し、4月1日から施行されています。10年ごとの支給で、10年前は50万円だった『特別弔慰金』の額は自動的に1割増額されています>
<この特別弔慰金支給のために今年度予算に計上された事務費は12億円です>
一方で、民間人や元植民地出身の元戦犯・抑留者らへの補償はゼロのまま。
<戦後処理における軍/民、内/外の格差を是正すべき戦後80年を前に逆に格差は広がってしまいました>
その上で政府に求めています。
<私たちは抽象的な文言より、「戦後80年」のけじめをつける具体的な措置をとっていただきたいのです。その実現のためには、もっと多くの世論の後押しが必要です>
翌4月19日、4団体は共同での初めての街頭デモを東京の日比谷公園から銀座にかけ、行いました。約100人が参加し、「今国会での救済法の成立を」と訴えました。
コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています
生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、コモンズの活動をご支援ください。 → 寄付でサポートする